バイオテクノロジーの常識が変わる!? 「遺伝の法則『優性』『劣性』やめます」
みなさんこんにちは!バイオサイエンス専攻教員の安達です。
新聞でおもしろい記事を発見したので、みなさんにも紹介しますね :a6:
バイオテクノロジーの常識が変わる!?
2017.9.7 朝日新聞朝刊 「遺伝の法則『優性』『劣性』やめます」
今、学校の授業で生物学を履修している方や高校の生物の先生にとって、
今まで「常識」だった知識が変わるかもしれません!
皆さんは「メンデルの遺伝の法則」を憶えていますか?
「メンデルの遺伝の法則」は、「分離の法則」「独立の法則」「優性の法則」の3種類があります。
ご存じのとおりメンデルはエンドウマメを使った研究で、親の性質(形質)が子に伝わるのは、何らかの粒子状の物質が関わっているという仮説を立てました(粒子説といわれています) :a2:
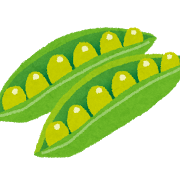
この物質をのちにウィリアム・ベイトソンが「遺伝子」と名付け、今日、その遺伝子の本体がDNA(デオキシリボ核酸)であることが分かっています。
このメンデルの法則のうち「優性の法則」は、両親それぞれから受け継いだ性質(形質)のうち一方が現れ、もう一方が現れない現象を説明するものです。
この時、現れる方を「優性」、現れない方を「劣性」と呼んで分けています :a2:

この「優性の法則」の優劣は、単にある特長(性質)が現れやすいか現れにくいかを表現しているのですが、漢字の語感から一方が優れていて、他方が劣っているような印象を与えてしまう場合があります :c13:
そこで、日本遺伝学学会がこの誤解や偏見を生じしやすい表現を変えて「優性→顕性」、「劣性→潜性」と言い換える提言をしました。
学会内では今後この新しい用語を使用していきますが、教科書の用語も変えて欲しいと、文部科学省に伝えるようです :c11:
もし、今後教科書などの用語も変われば、今まで優性・劣性で覚えていたことが通用しなくなるかもしれません :a13:
今後のニュースに注目です!



