【人工知能とバイオサイエンス】仮想科学者がコロナのワクチンを設計する!?
目次
まるで映画の世界…
実は、AIがコロナワクチンを作れる時代になりました。
スタンフォード大学の「Virtual Lab(仮想研究室)」の仮想科学者(AI)がコロナウイルスに有効な新しいワクチン抗体を92個設計。
そのうち2つが実際の実験で効果を示すという、驚きの成果が得られました。
この研究成果は、科学雑誌『Nature』にも掲載されています。
「The Virtual Lab of AI agents designs new SARS-CoV-2 nanobodies」
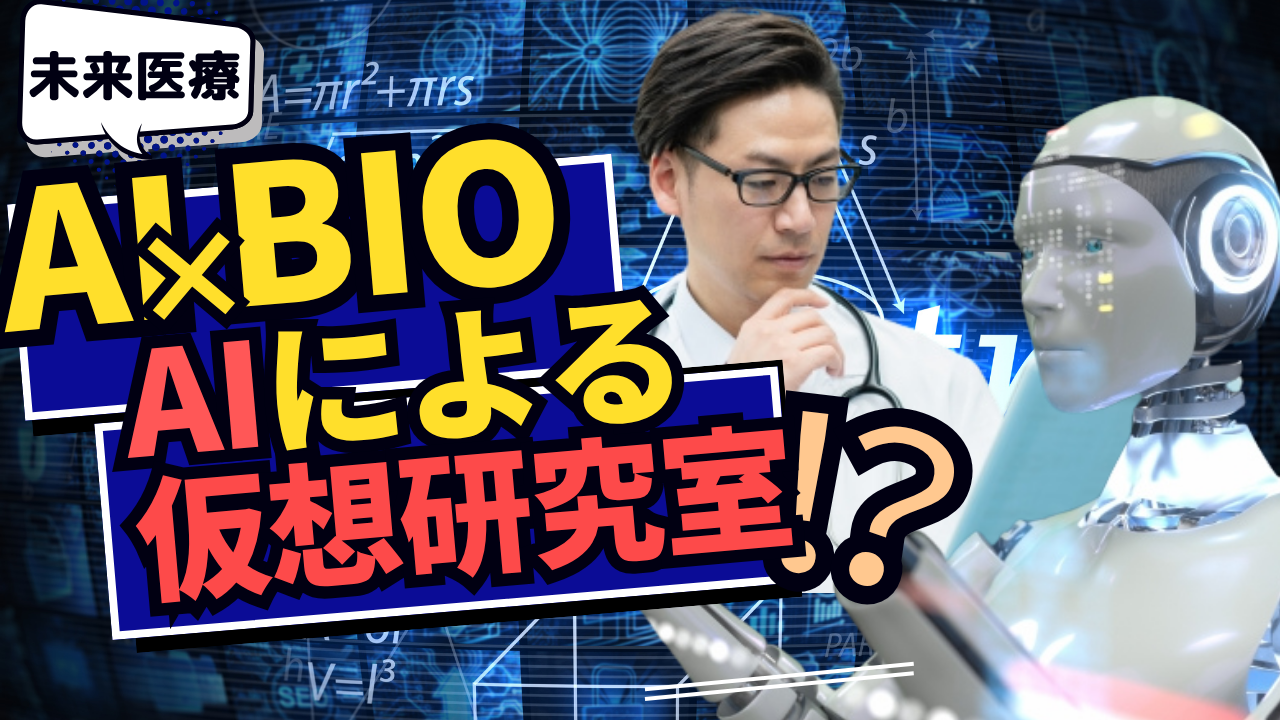
今回の研究は、AIが単なる“道具”ではなく、“共同研究者”として活躍する可能性を示すものであり、
まさに新しい研究スタイルの幕開けとも言えるでしょう。
しかもAIがすべてを担ったわけではなく、その力を最大限に発揮するために人間の研究者が重要な役割を果たしているのです。
このブログでは、「AIと人間、両方の力を活かしてこそ生まれる研究の未来」について、
高校生の皆さんにも分かりやすくお伝えします!
映画のような世界が現実に! AIが“研究チーム”になった日
スタンフォード大学の「Virtual Lab(仮想ラボ)」では、
AIが主任研究者や免疫学者、計算生物学者など複数の役割を持った“仮想科学者”として活動。
普通なら数カ月かかる構想を、わずか数日で実行に移すスピード感。
これまでにない研究スタイルが、現実になりつつあります。
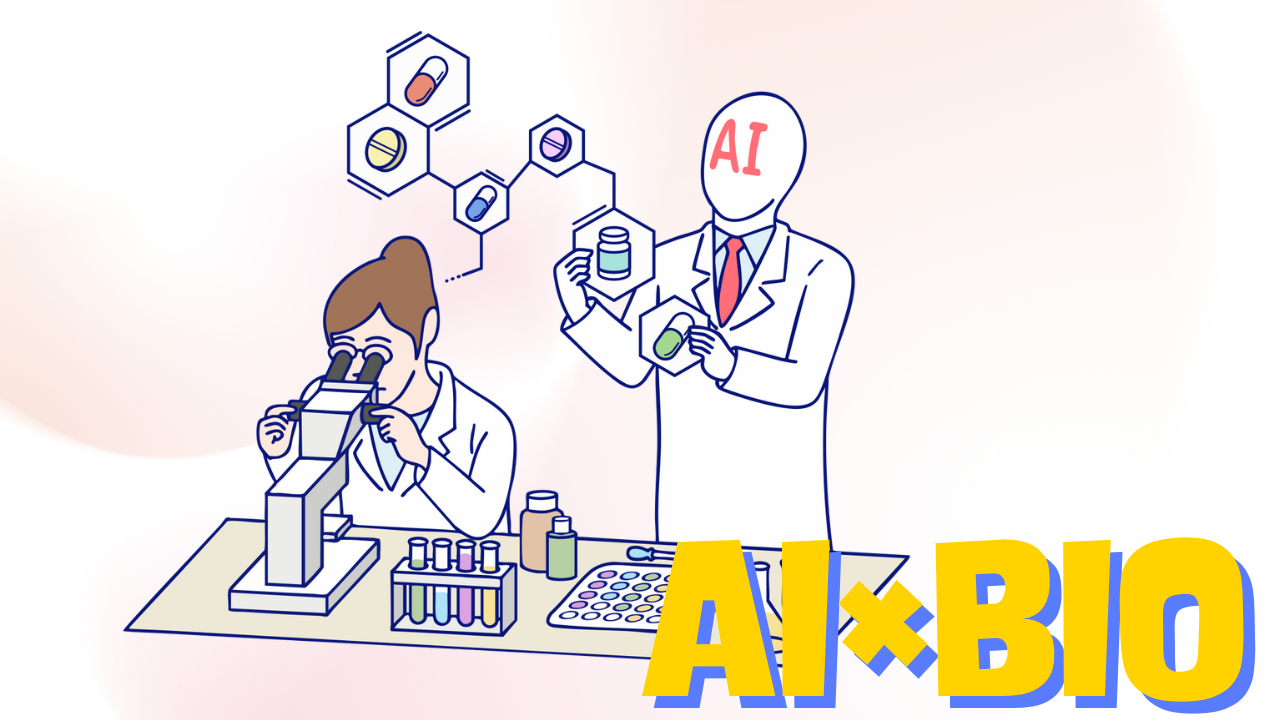
92個のナノボディ候補、驚きの効率!
AIはコロナウイルスに対するナノボディ(抗体断片)を設計。
その中から、実際にウイルスに効くと確認されたものが2つも見つかったのです。
これは、通常の研究と比較しても非常に高い成功率。
ナノボディ(VHH抗体)とは?
ラクダ科動物(アルパカなど)がもつ、小さく安定した抗体の断片
・高温やpH変化にも強く、小さいので狭い場所にも届きやすい
・関節リウマチ治療やがん免疫療法にも利用されている注目の技術
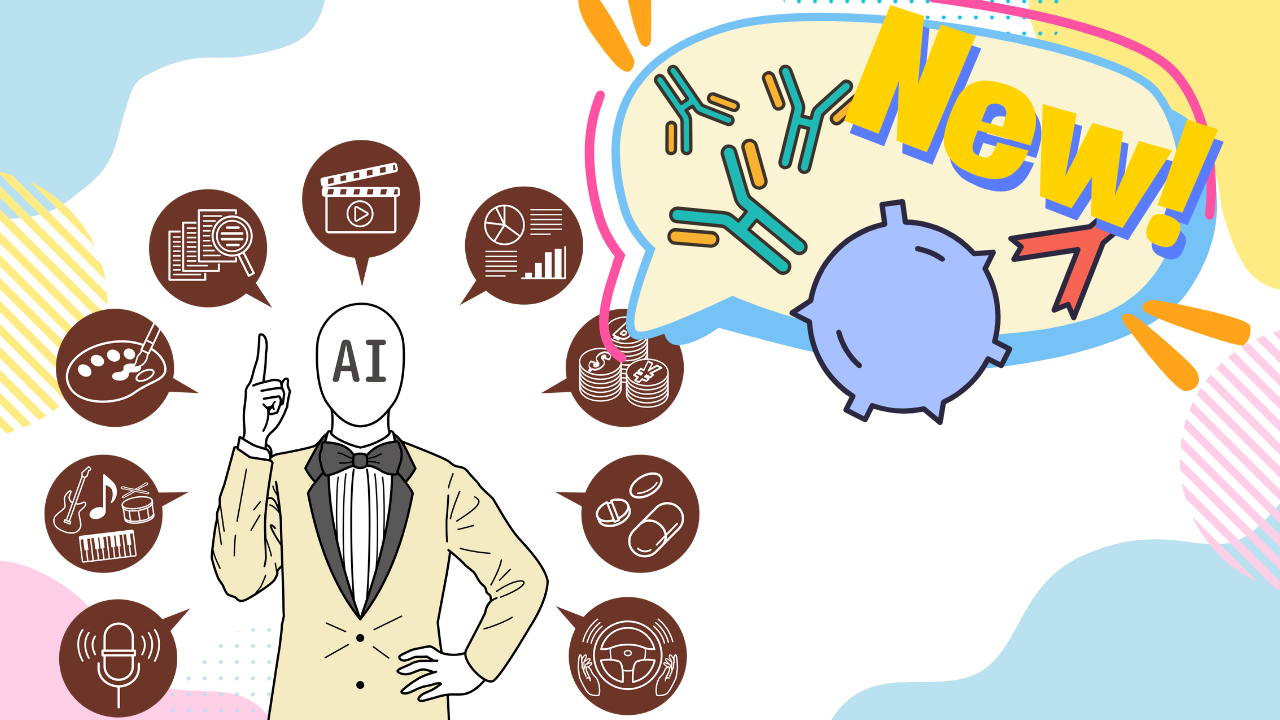
AIだけじゃない!人間の“目”も不可欠
AIが担ったのは、設計・シミュレーション・解析などの部分で
実際にAIを活かし、実験などを行って研究として完成させるのは人間の役割です。
研究テーマの決定、目標の設定
ディスカッションへの参加と軌道修正
ナノボディ抗体の実際の合成と実験
研究成果をまとめ、論文としてNatureに投稿&発表
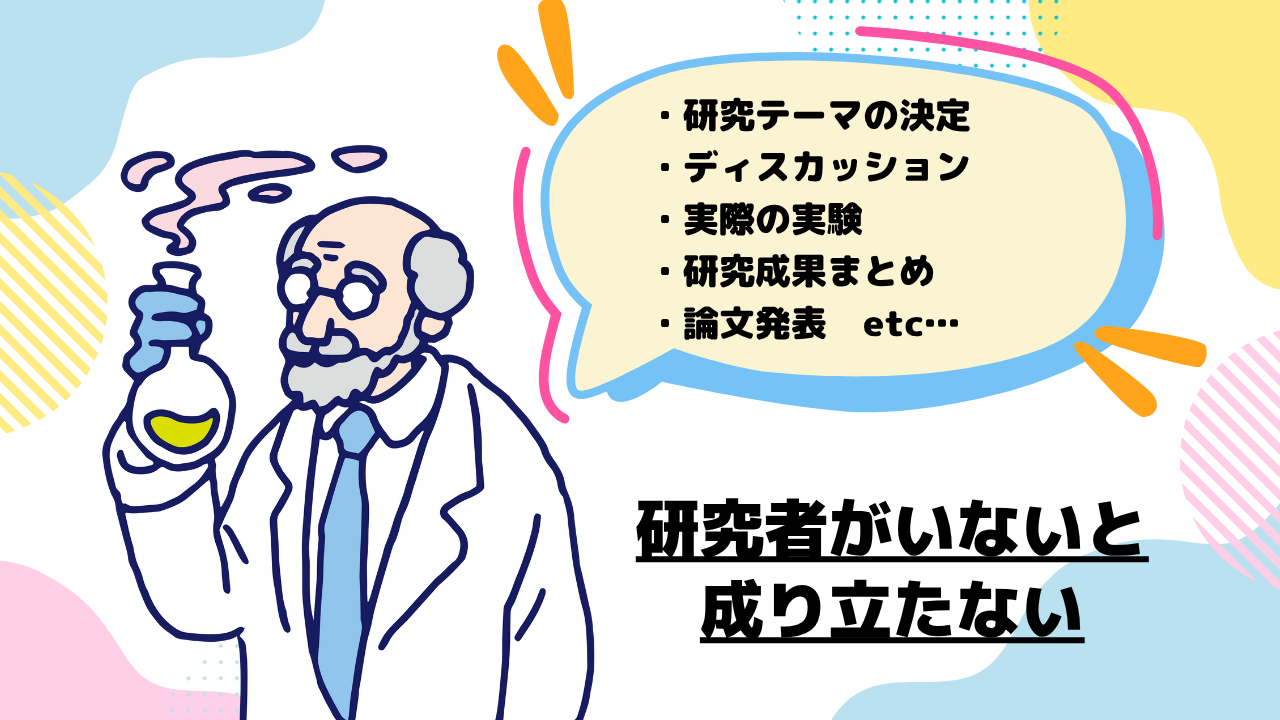
AI×人間、タッグが未来をつくる
AIは確かに設計や解析のスピードにおいて非常に優れています。
しかし、背景知識の活用、研究の方向性の判断、倫理的な視点、そして創造力や実験力は、人間研究者にしかできないこと。
実際に研究に関わったジョン・パク博士もこう述べています。
「AIに置き換えられるどころか、より多くの実験案が得られ、自分の研究はむしろ活性化した」
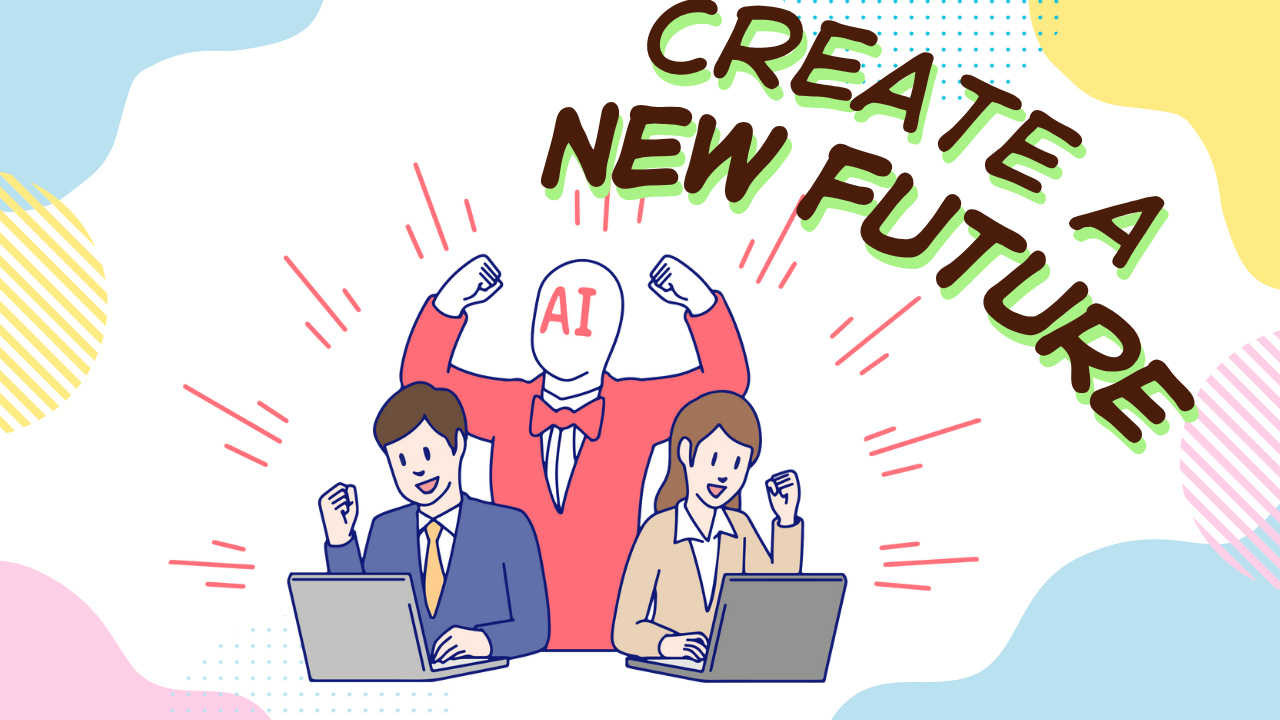
大阪ハイテクで学ぶ、“未来の研究者”への道
AIの力で研究が加速する時代。
でも、「何を研究し、どう検証し、どう社会に活かすか」を決めるのは人間研究者の使命です。
大阪ハイテクには、人工知能学科とバイオ・再生医療学科があり、未来の“AI×研究者”として活躍する可能性がここにあります。
バイオ・再生医療学科で研究者の道を目指してみませんか?



