授業を覗き見🌙夜間部2年生 新カリキュラム集中講座『看護技術学』
目次
~『人と向き合う力』を学ぶ特別授業~

大阪ハイテクノロジー専門学校 臨床工学技士科 夜間部2年では、新カリキュラムの一環として『看護技術学』の集中講座を実施しました。
テーマは、「パーソナルコミュニケーション」。
医療現場での「伝える」「感じ取る」力を養う授業として、多くの学生にとって印象深い一日となりました。
👨⚕️講師紹介 ― 現場のリアルを知る“二刀流”の医療人
今回の講師は、淀川キリスト教病院で臨床工学技士と看護師の両資格を持ち、手術室などで活躍されている義久靖宏先生。
看護と工学、両方の視点を持つ先生ならではの講義は、臨床工学技士を目指す学生たちに刺激的な講義となりました。
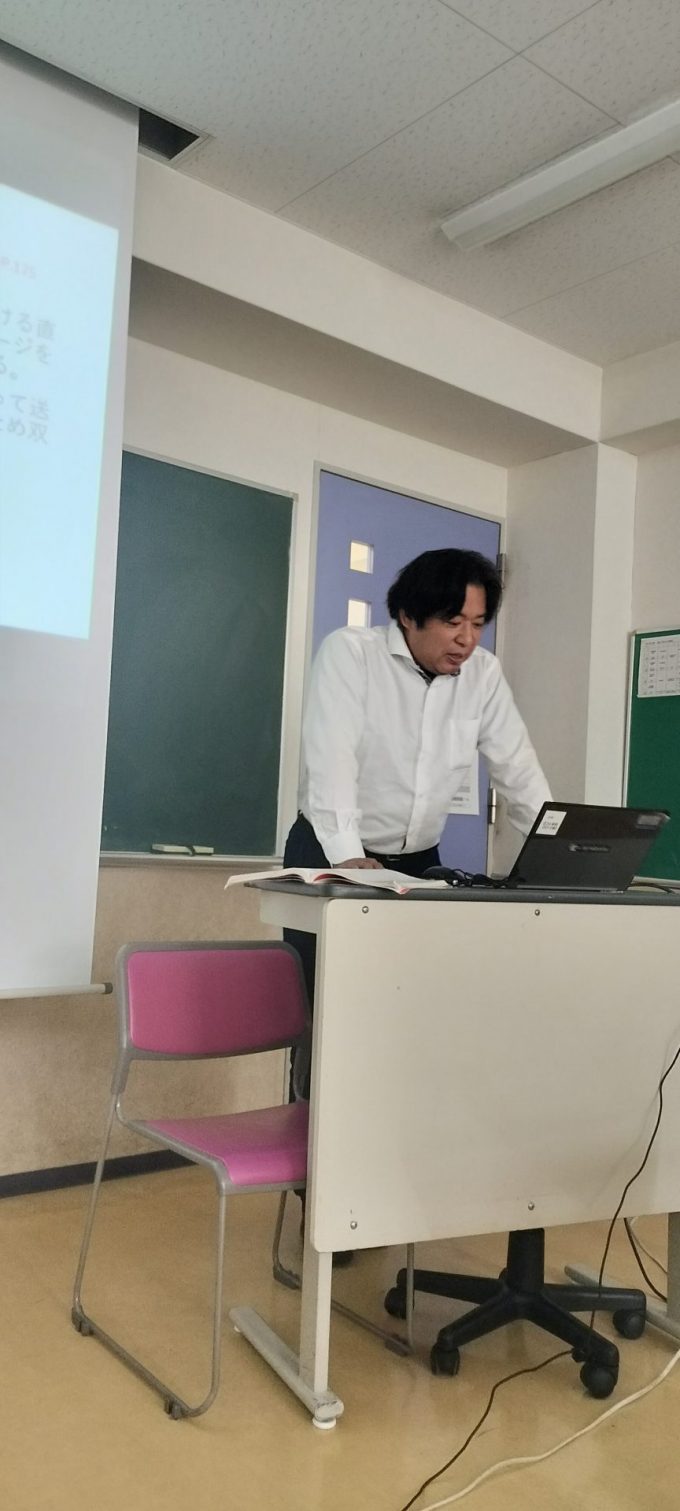
💬テーマ:「パーソナルコミュニケーション」とは?
授業ではまず、「パーソナルコミュニケーションとは何か?」という問いから始まりました。
言語による伝達だけでなく、 表情や目線、姿勢などの非言語的要素がコミュニケーションの約90%を占めるという事実に、多くの学生が驚きの表情を見せました。
義久先生は、「医療機器は“人を診る”ためにある。機械を扱う手の動きや目つきも、信頼を左右する大切な因子」と語り、学生たちに“態度で伝える力”の大切さを説かれました。
🌸日本人の文化に根ざしたコミュニケーションの理解
講義では、日本人特有のコミュニケーション文化についても触れられました。
-
察する文化:言葉にしない思いやりを大切にするが、医療では“言語化する力”が求められる。
-
恥の文化:他人の評価を意識しすぎず、自分の意見を伝える勇気を持つ。
-
甘え:患者さんを「甘やかす」ことも、時に安心を生むこともある。
-
プライバシー:今は患者さん自身が権利を主張する時代。尊重する姿勢が信頼につながる。
-
悲嘆反応:病気や喪失を経験する患者さんに寄り添う心のケアが欠かせない。
義久先生の「患者さんの言葉の奥にある“感情”を聴くことが医療者の第一歩」という言葉が印象的でした。
👀学生の声 ― “気づき”と“変化”の連続
講義後の学生たちは、それぞれに新しい発見を感じていました。
「非言語が9割と聞いて、目や表情の大切さを実感しました。普段から相手の表情をもっと意識したいと思いました。」
「“医療機器は人を診るためにある”という言葉にハッとしました。自分の動作や目線も医療の一部なんだと感じました。」
「日本人の“察する文化”を改めて考えさせられました。これからは、思っていることをしっかり伝える努力をしたいです。」
「患者さんとのやり取りを想定したロールプレイで、自分の話し方の癖に気づきました。相手に安心感を与える声のトーンを練習したいです。」
学生たちは、ただ知識を学ぶだけでなく、“人と人との関わり”の難しさと奥深さを体感しました。
✨まとめ ― 技術だけでなく「心」を磨く授業
今回の『看護技術学』集中講座は、臨床工学技士としての技術力と人間力を両立させるための貴重な学びの時間となりました。
義久先生の「患者さんの立場に立って考える力を持つことが、真の医療者の第一歩」という言葉を胸に、学生たちは次のステージへと歩みを進めます。
大阪ハイテクノロジー専門学校 臨床工学技士科 夜間部
「人と医療をつなぐ臨床工学技士」へ——学びは日々、進化しています。



